【迷宮在住の野良スライム、ひょんなことから新米冒険者の胸ポケットにお引っ越しする事になる。───スライムに生まれ変わった元勇者の僕が可愛い女の子冒険者に拾われちゃった!?表で可愛がられ裏では無双する充実のスライム生活が始まる!───(その2)】
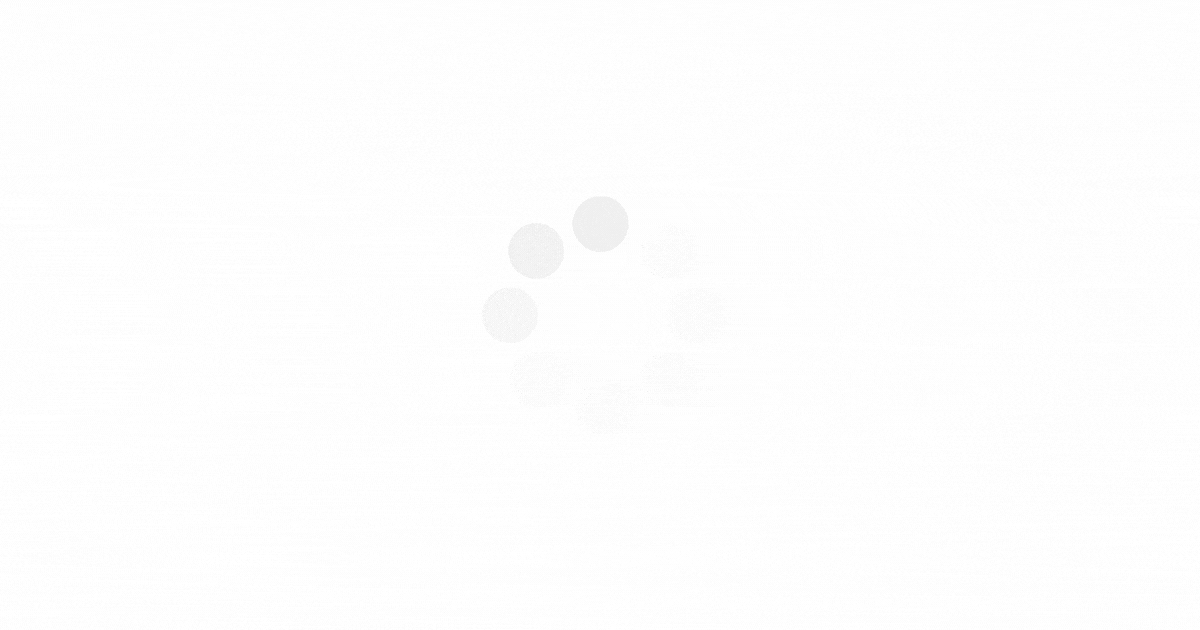
淫獄迷宮は、住んでいるモンスターの性質を除けばよくあるタイプのダンジョンだ。
人工物などもなく、自然の洞窟のような場所が広がっている。
自然の洞窟のような場所、というように、普通の洞窟とダンジョンでは明らかに違う箇所がある。
モンスターと遭遇するまでもなく判別は可能で、ダンジョンは普通の洞窟のように真っ暗になることもなく、常に日陰のような薄ぼんやりとした光に照らされている。
これはダンジョンが生きているから起こる現象だと言われていて、ダンジョンを構成する構造物に魔力が含まれているのが原因だった。
以前勇者だった頃の僕は実際に光源はどこから発生するのか調べたことがある。ダンジョンが生きている、という事に異論はなかったのだが、生きているからといってなぜ光るのか、その理屈がよく分からなかったからだ。
結果として、世間一般で言われていることは概ね正解だということが分かった。ダンジョンを構成する物質には魔力を溜め込み光に変換する魔法が組まれていて、それは動物の営みのように自然に形成されていた。
ダンジョンは様々な恩恵をもたらせてくれる。潤沢な魔力、魔力によって育まれた豊富な資源。そこに光も加われば、生きていくには十分だ。
そうやって引き寄せられたモンスターや動物や人間を、ダンジョンは自分の餌としている。死ねば命を、死ななくても生命力そのものを、ダンジョンは少しずつ食べて吸収している。
中には大陸を繋いでしまうほど大きくなるものもある。僕は行った事はないけれど、話を聞くにとてつもない魔境だと言う噂だ。
現在僕がいるこのダンジョンは中堅どころくらいだろう。広大ではないが、けっして狭くはない場所だ。
このダンジョンそのものは自然物で間違いない。ただそこに生息しているモンスターの生態は弄られていた。
「ひょわええッッ!!な、なにこれェ…ッ!!?」
そう、ぬらぬらと触手を揺らめかせる、目の前のモンスターのように。
植物と動物の特徴をあわせ持つモンスターが僕らの前に立ちはだかる。うねうねと動く様子は見ていて気分のいいものではない。
現に女の子も引いて距離を取っている。対処としてはとても正しい。
僕は胸ポケットからひょこりと顔を覗かせて、目の前のモンスターを観察した。
このダンジョン内の触手型モンスターは数種類いる。触手が細いもの、太いもの。移動するもの、移動しないもの。どれも共通するものは、獲物を性的になぶるために触手の形が進化している事だ。
ヒダがたくさんついていたり、吸盤が付いていたり、中には明らかに男のアレを模した形だったりする。
いま目の前にいるのは吸盤が付いているタイプだ。これがもし男のアレタイプだったら、僕はすぐに女の子の目を塞いで聖魔法で消し炭にしていただろう。
───どうする?倒す?逃げる?
このダンジョンに来た女の子の目的が分からないので、どう対処すればいいかもいまいち判断できない。もしモンスターの素材が目当てだったら、下手に手を出せば素材ごとダメにしてしまう。
とりあえず静観していると、女の子が大ぶりのナイフを抜いて戦闘する意思を見せた。
「こ、こんな所で引き返してちゃ、お姉ちゃんが…っ。頑張らなくちゃ!」
自分を鼓舞する為の言葉が彼女の口からこぼれ落ちる。どうやら彼女には姉がいて、このダンジョンへ来ることになった理由にもなっているらしい。
思わぬところでひとつの情報を得た。このまま彼女と一緒に居れば、そのうちダンジョンへ来ることになった具体的な目的も分かるかもしれない。
そうしたら僕の力で目的を達成させて、さっさとこんな場所から彼女を脱出させることができる。ついでに、僕も脱出だ。
緊張に強張る彼女の胸の圧迫を受けながら、僕も魔力を練り始めた。
僕らの戦う意思を感じたのか。触手がぬらぬらとしたピンク色の粘液を滴らせながら、こちらへと狙いを定めてくる。
ヒュッと鋭い息をひとつ吐いて、女の子が触手へと突進した。
───戦闘開始!
僕は彼女に知られないように、聖魔法をいくつか展開した。
───常時結界形成。
───身体能力強化。
───体力継続回復。
攻撃魔法は使わない。彼女が動けるうちはあくまでサポートに留めておく。
僕の内助の功もあって、先程のコボルト戦よりも彼女はよく動いてくれた。向かってくる触手を躱し、端を切り捨てて後退する。
動き方はぎこちないが、戦闘の基本は出来ている。実践こそ少なそうだけど、誰かに戦闘の仕方をきちんと教わっていたのだろう。
「い、いける…っかも。…たぁーっ!」
自信を付けた彼女が更に切り込んでいく。多少触手がかすめても僕の結界がすべて弾くし、膂力を上げたから与えるダメージも増えている。体力も回復しているから長い戦闘にも耐えられる。正直、負ける要素がない。
このまま彼女に任せよう。そう思って胸ポケットにススっと戻ろうとすると、辺りに甘ったるい匂いが漂っていることに気が付いた。
切った触手の断面からぼたぼたと液体が流れている。粘液を更に濃くしたようなどぎついピンク色だ。
おっと、いけない。僕はあわてて彼女に追加の聖魔法を放った。
───状態異常無効。
触手型モンスターの体液はいわゆる媚薬効果があり、どんな屈強な冒険者でも下手をすれば格下の魔物にヤラれる危険性がある。
むしろ媚薬に頭をおかしくされて、自分から罠に飛び込む可能性すらある。中毒になった冒険者がこの迷宮に繰り返しやって来るのを僕はもう何度も見てきた。
あられもない犠牲者たちの姿を思い出し、もしそれが彼女だったらと想像する。
あんな事やこんな事になっている彼女の姿…。
……。
…………。
………………。
───状態異常無効!
僕はあわてて自分にも聖魔法を放ち、うっかりホーリースライムからエロスライムにスライド進化することを阻止しておいた。
「ふぅ、ふぅ…。や、やったぁ!……よね?」
僕が勝手に窮地に陥っている間に、女の子は問題なく触手を倒しきったようだ。くてりと力を失くしている触手を、ツンツンと大ぶりのナイフで突いている。
記念すべき初勝利の瞬間を見逃してしまった。僕はほんの少しガッカリしつつも、すぐに気持ちを切り替えて彼女を安心させることにした。
───大丈夫。もう起き上がってこないよ。
僕はぴょこっと胸ポケットから抜け出すと、触手のそばに着地した。触手の近くにぴょんぴょんと近づいて、何も起きない事を証明する。
───ほら、大丈夫でしょう?
でも女の子は僕の意図に気付かなかったようで、慌てて僕の体を両手で掬い上げた。
「あ、あぶないよっ!もし生きてたら、パクッて食べられちゃうよ!」
すごく心配されてしまった。ちょっと嬉しいかもしれない。
ご機嫌になった僕は、ついつい手のひらの上でコロコロしてしまう。すると彼女は触手の横をそのまま通り過ぎようとした。
───あれ。こいつの粘液、採取しないの?
こういった触手型モンスターの粘液は薬の材料になる事が多い。特に淫獄迷宮の触手の粘液は高く売れるらしいので、見逃すのは勿体ない。
「あっまた!」
僕は居心地のいい手のひらからぴょいっと脱走して、もう一度触手のそばに近づいた。そうして、ほんの少しだけ体の表面を崩してにょいんと小さな突起を作る。
腕とか指とか、そんなイメージだ。これくらいの形状変化なら変に思われないだろうと思って作ってみた。
その突起でちょいちょいと触手を突いたあとに、ぷるるんっと女の子の方に振り向いてみる。僕の意図が伝わっていないのか、不思議そうな表情をしている。
とりあえずもう一回ちょいちょい触手を突いてみる。…何度か繰り返せば伝わるだろうか?
ちょいちょい、ぷるるんっ。
ちょいちょい、ぷるるんっ。
何故だろうか。振り返る度に、女の子の眉が下がっていく。
「……もしかしてその触手、食べたいの?」
───いや。違うよ!
思わぬ誤解をされそうになって僕は慌てた。引かれ気味なのがちょっと悲しい。
───僕はあんなの、食べないよ!
もう触手なんて構っている場合じゃない。僕はシュッ!と速攻で彼女の元へ帰ると、差し出された両手の上でゴロンゴロンと転がって身の潔白を主張した。
そんな一幕がありながらも、僕らは先に進んで行った。進むというか…僕的には元居た場所に戻っているのだけど、女の子目線では進んでいるのだ。
そうして気付いたのは、彼女がこのダンジョンへ来た目的はモンスターではなさそうだという事だった。
何せ出来るだけ戦闘は避けようとしているし、いざ戦闘になってモンスターを倒しても素材はすべてスルーしている。
代わりにダンジョンのあちこちに目をやって、何かを探しているようだった。多分、薬草とか鉱石とか、そういうモンスター由来じゃない素材が欲しいんじゃないだろうか。
僕が胸の弾力を楽しみつつ彼女の目的について推察していると、ポケットの上からぽんぽんと優しく叩かれた。
ぴょこっと顔を出すと、女の子が優しく話しかけてくる。
「ちょっと休憩。スライムさんも、付き合ってくれる?」
───いいとも!
ぴょいっ!と跳ねて返事をする。ほんの少し疲れた顔をした彼女は、僕の様子を見て楽しそうに笑ってくれた。
女の子は外からは見えにくい場所に腰を下ろして、ふーっと大きく息を吐いている。相当疲れているようだ。
密かに体力回復の魔法を使っているけれど、別に万能と言うわけではない。体の疲れは少しずつ溜まってくるし、精神までは癒やせない。いつモンスターと遭遇するかも分からないダンジョンでは気疲れのひとつもするだろう。
僕は元勇者だったのでひとりでもダンジョンをずいずい攻略していたが、彼女はそんなに経験もなさそうなので仕方ない。あまり無理はして欲しくないな、と少し心配に思う。
僕は少しでも彼女の助けになるように、にょいんと突起を作ってふくらはぎ辺りをモミモミする事にした。
足のケアって意外と馬鹿にならない。風呂がないような宿でも、桶一杯の水をもらって足を洗うと生まれ変わったようにサッパリする。そうして、すごくリラックスできたり、びっくりするくらい気力が湧いてきたりする。
もみもみ。もみもみ。生地が厚いからきちんと揉めているのか分からない。でも、もみもみ。もみもみ…。
「あはは、スライムさん。わたしの足で遊んでるの?」
魔法では解せない疲れを癒そうとする僕を、じゃれていると勘違いした女の子がおかしそうに笑っている。
───違うよ!僕は真剣なんだよ!
抗議をするようにぴょんぴょん跳ねると、その様子も面白かったようで女の子はますます笑ってしまった。
───まぁ、いいけど。
少しでも気が晴れたなら、ある意味僕の目的は達成されたという事だ。勘違いされて笑われてしまったけど、僕もそんなに悪い気分じゃなかった。
さて、改めて続きのもみもみをしようかな、と考えていると、「スライムさん、ちょっと待ってて」と女の子がゴソゴソと背負っていた荷物を漁り始めた。
小さな袋を取り出して、そこから薬草や木の実、干し肉やチーズなどの携帯食料を手のひらに乗せて見せてくれる。
「お腹すいてない?スライムは何でも食べるって聞くけど、この中から食べたいものはあるかな」
何と女の子は、偶然出会った野良スライムに食事を分けてくれるつもりらしい。
僕は感動にブルブル震えてしまった。うっかり丸い形から崩れそうになりつつ、女の子が差し出した手のひらにススっと近寄っていく。
薬草、木の実、干し肉、チーズ。
ラインナップは先ほどと同じなのに、女の子の言葉を聞いた後だととてもキラキラして見える。
正直、僕はグルメなスライムだと思う。やたらと強い聖属性の草ばかり食べていて、『アイテムボックス』の中には膨大な量のストックが眠っている。
ちなみに僕がスライムになってから最初に意識を取り戻したのは、ダンジョンの中でも特殊な場所だった。
子どもたちが追いかけっこをしてもなお余るようなやたらと広い部屋で、出入口は自然と崩れたような狭い穴しかなく、他の魔物も入って来ない、まさに僕だけの秘密部屋だった。
そこにわさわさと生えていた草が僕の主食になった。食べても食べても次々生えて来る草だったので、今はアイテムボックスの中に数年分くらいのストックはあると思う。
僕は女の子の手のひらを改めて見た。この中から食べるとしたら、薬草だろうか。ただ僕はグルメなスライム、食べて美味しいと思えるかどうかは分からない。
現に主食の草に埋もれるように別の種類の草がポツポツと生えていたけれど、苦みが強くて僕はあまり好きではなかった。たぶんあれは雑草だと思う。
僕はちょっと悩んで、結局薬草を1枚頂くことにした。他は明確に女の子の食べ物だと分かるし、薬草なら僕の聖魔法が代わりになれる。
そうと決めたら他の食べ物を踏まないようにぴょんと手のひらに移って、目的の薬草をもしゃもしゃと食べてみた。たぶん外からだとじゅわわ…と溶けているように見えると思う。
邪魔になるといけないので、すぐに手のひらからぴょこんと降りる。
もしゃもしゃ、じゅわわ…。僕の体の面積からしたら巨大な草が、どんどん消化されていく。その様子を女の子が楽しそうに見守っていた。
「美味しい?」
女の子の言葉にぴょんっ!と跳ねて返事をする。僕はグルメなスライム、けれどもそのお味は。
───意外と……おいしいじゃないかっ!
冒険者がよく使う普通の薬草だけど、雑草なんかより断然このみの味だった。
「じゃあわたしも、いただきます」
ご機嫌で揺れる僕を見ながら、女の子も自分の食事をし始めた。水筒からごくごくと水を飲み、干し肉をガシガシと齧っている。
ワイルド…!と思いながら見ていると、女の子は自分の手のひらにお水を垂らして、僕に差し出してくれた。
「喉もきっと渇いているよね。はい、どうぞ」
至れり尽くせりである。先ほどまで僕が奉仕する側だと思っていたが、どうやらそれは間違いだったようだ。
うぬぼれていた自分に恥ずかしくなりながら、遠慮なく彼女の手のひらにぴょこんと舞い戻る。
スライムの体は見た目通り水分量が多いので、補給もそれなりに必要だ。
秘密の部屋には水源がなかったので、最初の頃は草に付いていた朝露をせっせと集めて取り込んでいた。活動範囲が広がるとそれなりに綺麗な水源を見つけることができたので、今も僕のアイテムボックスにはけっこうな量の水が入っている。たまに助けた冒険者の水筒の中身を拝借することもあった。
なのでもし女の子の飲み水が枯渇したとしても問題ない。僕は遠慮なく手のひらの器に注がれた水をゴクゴクと飲んだ。
「…スライムさんがいてくれて良かった」
女の子が唐突にぽつりと呟く。
どうしたの?というように顔を上げると、僕を慈しむような表情で見ている女の子がいた。
どきん。僕の『核』が振動する。こんな風に人から見られた事なんて本当に久しぶりかもしれない。
何せ僕は勇者だったので…。頼りにはされても、慈しまれる側ではなかったのだ。僕が昔を思い出して物思いにふけっていると、さらに女の子が口を開いた。
「お姉ちゃんの為にって飛び出してきたけど、スライムさんがいなかったら怖くてすぐ逃げてたかも」
また『お姉ちゃん』だ。もしかしたら、彼女がダンジョンに来た理由が語られるかもしれない。僕はプルプルと震えて続きを促した。
女の子も誰かに話したかったんだろう。僕を相手に、何故こんなダンジョンに来たのかを教えてくれた。
「…あのね、お姉ちゃん体が弱いの。今まではお母さんが特別な薬を作ってくれてたんだけど、その材料が貴重品で、中々手に入らないものなんだ。今年は特に不作で…。お母さんは何とかするって都会まで探しに行ってるけど、帰ってくるまでに薬が持つかどうか分からない。だから、わたしが直接材料を採りに来たの。…迷宮で、時々手に入る草だって聞いたから」
そこまで言うと、女の子は黙った。本当に手に入るのか不安になっているのかもしれない。
僕は『貴重品』『草』というキーワードから、ある存在を思い浮かべた。
秘密の部屋にわっさわっさと生えていたもの。その割にはダンジョン内ではとんと姿を見かけないもの。
そう、僕の主食である聖属性の草である。
思い至れば即実行。僕はシュッ!と女の子から見えない位置に移動した。
「スライムさん、どこ行くのっ!」
女の子の焦った声が聞こえる。言い訳できないのが心苦しい。
───ごめんね、すぐに戻るよ。
心の中で返事をしながら、ちょっとした隙間に潜り込む。
女の子から見えない場所にたどり着いたあと、僕は大急ぎでアイテムボックスから聖属性の草を取り出した。時間が止まっているから、草の状態はツヤツヤとした新鮮なままだ。ちなみに根っこ付きだ。
薬に使う部分は葉っぱだけとは限らないから、葉も茎も根っこも付いているものをチョイスしてみた。
このダンジョンを出たとして、もしかしたら他では手に入らない草の可能性がある。数年分くらいのストックはあるけれど、念には念をと外で育てられるように完全な状態の草も用意していた。
下手したらストックの最後のほうまで出番はないかもと思っていたけれど、まさかこんなに早く必要になる日がくるとは…。
僕は自分の用意周到さを褒めちぎりながら、シュッ!と急いで女の子の元に戻った。
「あ、スライムさん。よかった!いきなりどうしたの。もしかして、おしっこ?」
───ち、ちがうよ!女の子がそんな……だめだよっ!
女の子の口からまろび出るシモな話題にちょっぴりドギマギしながら、すすっと秘蔵の草を差し出してみる。
「え、スライムさん。この草…!」
───そう、きみが探していた草だよ!これでこの迷宮から帰れるね!
葉っぱも茎も根っこも揃った『The・完全体!』な草を見て、女の子が満面の笑顔になる。
「すごい、迷宮の中に草が生えてたんだね!じゃあ、やっぱり探してる薬の材料もどこかにあるんだ!」
───ん?違うよ、これがこの草だよ。よく見て、ほら。
ずずい、とさらに出すと、女の子がそっと受け取ってくれる。
「さっきの薬草のお礼かな?こんなに大きい草、持って来るの大変だったでしょう。でもこれは探してる草じゃないから、スライムさんが食べていいよ」
───え?
衝撃的なことをにっこりと笑いながら言った女の子は、僕が自信満々で差し出した草を丁寧な仕草で返してくれた。
───そ、そんな…!この草じゃないのっ??
僕はびっくりしながら、返された草を思わずムシャムシャと食べていた。さっぱりとした風味で、ほのかな甘みがする恩草。こんなに美味しくてすごい草なのに、特別な薬の原料じゃないなんて…。
信じられない気持ちになりつつも、彼女が違うと言うならそうなのだろうと納得する。きっとこの草は一目見て分かるくらい探している薬の材料とはまったく違う形をしているんだ。
しょんぼりしていると、女の子は僕を両手で掬い上げた。
「よし、休憩おわり!スライムさん、もうちょっとだけ付き合ってくれる?薬の材料も大切だけど、あなたの飼い主さんも探さなくちゃね」
僕を思いやる言葉にちょっと気分が浮上する。飼い主なんていないけど、彼女は僕の事を一生懸命考えてくれている。
気持ちを反映してぴょこぴょこと小刻みに跳ね始めた僕を、彼女は再び胸ポケットの出口を開けて誘ってくれた。もちろん僕は自分からすすっと魅惑の暗闇へと入っていく。
───ううん、相変わらずの弾力と柔らかさ。適度に湿度があるし暖かいし、何だか落ち着く…。
コトコトと鳴る心臓の音にうっとりしつつ、僕は胸の谷間に近いベストポジションに移動した。
「じゃあ、行こう!」
女の子の号令にむにんと頷く。
───分かった。サポートは任せて!
ちょっと出鼻は挫かれたけど、僕らのダンジョン探検はもう少しだけ続きそうだ。
それからしばらくの後、僕らは何度か敵に出くわしながらも少しずつ奥の方へ進んでいた。
小型の触手やコボルト、ゴブリンと言った弱めの敵に当たったのも良かった。ゴブリンの集団に囲まれた時はヒヤッとしたけれど、彼女を掴もうとする手を結界で弾いて、各個撃破する事ができた。
そうして気付いたのは、女の子の体は妙に聖魔法の効きが良いという事だった。彼女にかけた聖魔法は、自分にかけた聖魔法よりもより大きく効力を発揮する。
そういう体質なのか、それとも魔法の力を増大させるマジックアイテムでも持っているのか。
どちらにしろ、彼女の身が安全になるなら良い事だと思える。
「うーん、次は…こっちに行こう」
そして彼女は妙に勘が良い。分かれ道があったとして、必ず先に続く道の方を選んでいる。今も行き止まりになる方の道を横目に、僕の通ってきた道をまっすぐに進んでいた。
───確かこの先で禿げ散らかしたおっさん冒険者とすれ違ったっけ…。
僕が思い出していると、うおおぉぉぉ……、うおぉおぉぉぉ…。獣の声のようなものが響いてきた。
「この声…何だろう。コボルトともゴブリンとも違う。もしかして、トロールやオークとか?ま、まさか、オーガじゃないよね…?」
コボルトやゴブリンはともかく、今の女の子ではトロールやオーク、ましてやオーガとの戦闘は厳しいものがある。僕の全力のサポートをもってしても逃げ切れるかどうか分からない。いざとなったら僕自身が表に出て戦う必要があるだろう。
けれどこの声には聞き覚えがあった。
僕がぷるぷると小刻みに震えていると、女の子がとんでもない事を言い出した。
「よ、様子を見るだけなら…大丈夫かな?……わっスライムさん!?」
僕は抗議をするように、胸ポケットの中でぽよんぽよんと跳ねて暴れてみた。
───やめておこうよ!トラウマになるよ!
コボルトでもゴブリンでも、トロールやオークでも、ましてやオーガでもないこの野太い声には聞き覚えがあった。
僕が何度も聞いた声。何度助けてもキリがないと見切りをつけた原因のひとつでもある声。
そう、この声の正体は、禿げ散らかったおっさん冒険者である。